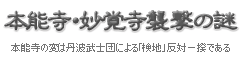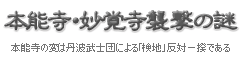信長が都鄙の迷惑を願みず、みだりに諸国を奪い取ったこと
神社・仏閣

<1.>に関して私には余り言うことがありません。
当時の社会的(民衆レベルの)生活基盤は宗教であったこと。日本であっても西洋であっても宗教を基盤として社会が動いていたこと、宗教の時代であったことを再確認すればよいと思います。
研究者が利用する一次史料は"はっ"と気が付いてみるとほとんどが宗教・神社仏閣がらみのものでしょう。
<2.>について。 私はこれに注目しました。
これはその当時、丹波で展開され始めていた「検地・城割り」政策に対する抵抗を示す言葉ではないかと考えました。
以前作成しておいたテキストを流用します。少し長いのですが、すみません。
これが私の「本能寺の変」考察の結論です。
● みだりに諸国を奪い取り
(『訂正・加筆』 76ページ)
「武功夜話」採録のこの文章を読んだとき、私は(私以外の人もそうだと思いますが)漠然と"武田氏征討、長曾我部氏征討、中国方面への侵攻"といった進行状況(押せ押せムード)をイメージしていました。
けれどもこの言葉を怒気を込めて発する彼らの身になって考えてみると、これと質を異にするイメージを抱くことが可能だということに気が付きました。
見ず知らずの(遠方にある)甲斐の国、土佐の国、中国方面の国々がどうなろうと、彼らにとって切実な問題にはなり得ないだろうと考えるのです。
彼らが"みだりに諸国を奪い取る"と信長を告発するとき、それは間接的には先に記したような信長による自国領土の量的拡大を指すのかもしれません。
また彼らは武田氏征討の時、一ケ月半に及ぶ出張(イクサに出かけること)をしなければならなかった。
そして追い打ちをかけるように今度は中国方面への出陣命令が下されたわけです。
「農作業に精を出さなければならないときに、いつ帰れるか判らない戦(イクサ)に再びかり出されるなんて…理不尽だ!」といった不満があったろうことが推測できます。
けれどもそれ以上に彼らにとって深刻だったのは丹波における「城割り・検地」、および「(これに抵抗する)国人層の粛正」ではなかったかと考えるのです。
信長像
遠藤周作他
「対論 たかが信長 されど信長」
(文芸春秋社、1992年6月刊)

つまり先の彼らの告発は「城割り・検地」によって追いつめられた"抵抗の叫び"ではなかったか? と考えるのです。
実際、自分の領地を「城割り・検地」施行に曝(さら)すことになれば、それは国人として彼らが先祖代々受け継いできた「在地支配の既得権」を根こそぎ奪い取られることを意味することになります。
信長の「みだりに諸国を奪い取る」方法(武士道)は旧来のそれとは全く質を異にするものなのです。
朝尾直弘氏の表現を借りれば、
配下の大名の所領支配にまで干渉する「(中世的武士)らしからぬ」信長の武士道は「(中世的武士)らしい」光秀の武士道と鋭い矛盾を有していた。すくなくとも光秀の家臣団には相当な抵抗があったと考えてよい(小学館「日本の歴史8 天下一統(1988年)」153ページ)
のです
(『ノート』 183ページ、『訂正・加筆』 21ページ)
。
天正十年時、たしかに信長は甲斐、四国(土佐)、中国方面へと自国の領土を拡大しようとしていたし、私たちもこうした進展状況に目を奪われます。
けれども信長はまさにこうした量的拡大を押し進めていくまっただ中において、同時進行的に「城割り・検地」を媒介にした自己権力の質的変革を遂行していったのです(いうまでもなくこの「城割り・検地」施行は、そのあとに家臣団の国替え=強制移住を想定します)。
これは"信長自身の自己変革"の外的実現と考えます。「城割り・検地」を媒介にした畿内の制圧は天下統一を実現するための「質」の確立(端緒=本質)。あとは量的拡大、という考え方です。
この一番大切な押さえどころを見逃してはならないと思います。
指導者(組織者)は自己に似せて組織を作る、という表現がピッタリと思います。
(H9.6.3)
<たとえ話>
「城割り・検地」政策が給人(武士団)、国人にとって天変地異の出来事であったことがどうも理解してもらえないようです。そこでたとえ話を一つ。
検地要具図
安藤博編「徳川幕府県治要略」(柏書房、1981年6月刊)
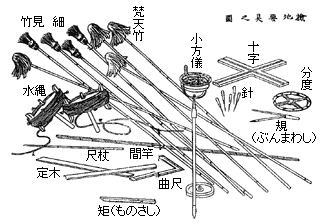
「(一戸建てでもアパートでもいいのですが)ある日突然あなたの家に何人もの税務役人およぴその請負業者がやってきました。
土足で家の中にあがりこみ、所有物(土地、建物、貴金属、車、あらゆる金目のもの)はもちろん預金通帳・株券までリストアップして調べ上げてたち去っていった。
何日かして"おまえは家族共々何々市何々村へ行くことを命ずる。現在おまえが所有する物は公的に没収する"と通告された」
なんでそんな突拍子もないとんでもないたとえ話をするんですか? と怪訝な思いをもたれるかもしれません。
「城割り・検地」施行は国人層にとってそのようなとんでもない言いがかりに映ったんです。
検地施行に頑強に抵抗せざるを待なかった彼らの切な気持ちに共感できるでしょう?
彼ら国人層を突き動かしたこの「危機感」に共鳴することが出来るか、出来ないか? これが「本能寺の変」解明への入り口です。
私はそう断定します。
既得権を剥奪されることに頑強に抵抗する人間の本性は、現在の行政改革をめぐる暗闘を見ればよく分かるでしょう。
<土佐の例>
秀吉の時代、土佐においても検地が行われた。
検地施行の役人が在所へ赴き、ある寺に宿した。危機感にかられた土豪たちはその宿所を焼き討ちにした。
こんな例があるんです。これなどは"土佐版 本能寺の変"といえるでしょう。
そして朝尾直弘氏のような超一級の研究者が「本能寺の変」勃発の背景として「給人(武士団)の検地に対する抵抗」を考えておられる。
このことをはっきり氏の文章において確認してください。
そして社会史学の威力に目を向けていただければと思うのです。
現在の日本歴史小説はどれもこれも社会史学的分析が抜け落ちています。私も偉そうなこといえませんけど。
<視角>
明治維新政府によって実施された土地改革(地租改正)を研究する場合、その(直接的)前史として織豊期の検地政策が研究対象として取り上げられる。
更に細かく見るならば織田信長による検地政策がその始源として考察される。
天正初めから既に検地は行われたけれど、その全面的展開は天正8年から開始された(『訂正・加筆 その二』19ページ~)。
ここを是非とも押さえていただきたい。本能寺の変はまさに日本中世社会が近世へ変質していくその瞬間において生起した事件なのです。
信長による検地を考える場合、先の明治維新政府による地租改正政策も視野に入れてください。
佐々木寛司著「地租改正」(中公新書)は手頃な手引き書です。
「本能寺の変~検地」と言っても私たちの生活に直接には何にも響かないように思える。
けれども見方を「現代的土地所有関係(の生成)」→「地租改正」→「検地」と問題をたぐり寄せるとき、「本能寺の変」は単なる過去のお話ではなく、生きているものとして・何かを訴えかけるものとして、心そして体に響いてくるのです。私にはそうなのです。
(H9.10.26)
{参考} 朝尾直弘氏・・・
信長の死は、やはり中世から近世への大きな転換点だったと思いますね。たとえば信長がやろうとした朝廷や公家の統制の問題とか、寺社勢力を統制するということがあります。そういったいわゆる中世に権力をもっていた勢力、荘園領主でもあった勢力や宗教勢力をひっくるめて、権力を取り上げてしまう。そして、いわばかたちばかりの権威の枠のなかにはめ込んでいく。実権は征夷大将軍あるいは天下人というものが握る。こういう社会へその後かわりますね。そうするとそういう大きな変わり目、どこでかわるんだろうということを煮詰めていくと、やはり信長のこの天正十年というあたりへいきます。その前と、そのあととの、両側から詰めてくると、まさにかわり目というところで本能寺の変が起きているということが言えると思うんです(角川書店「歴史誕生6」、1990年。都立中央図書館<開架>)。